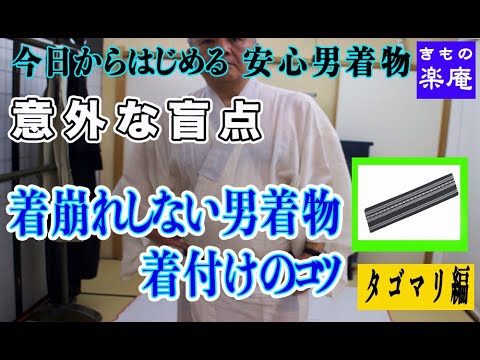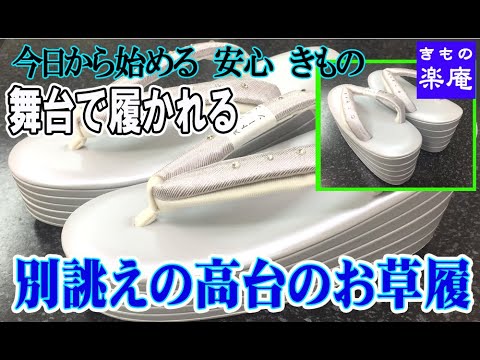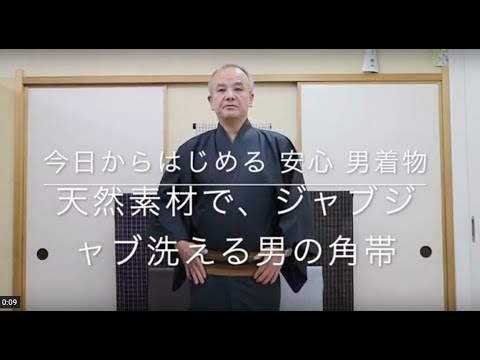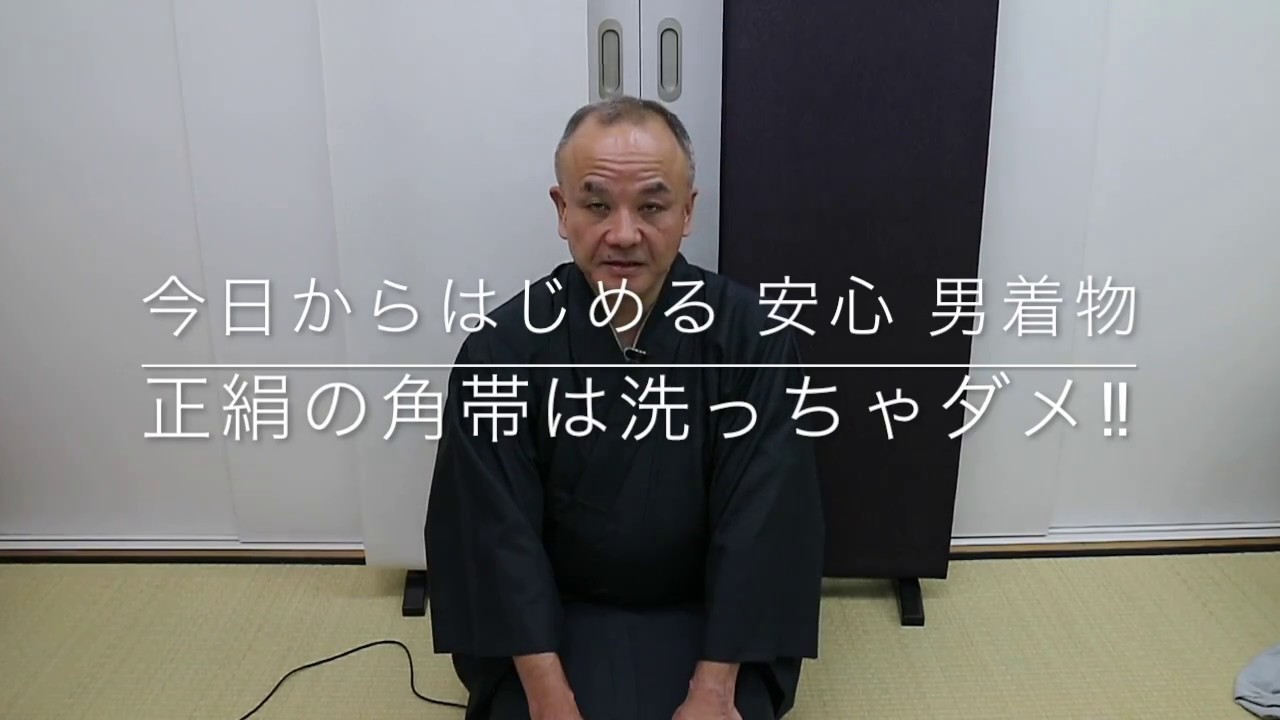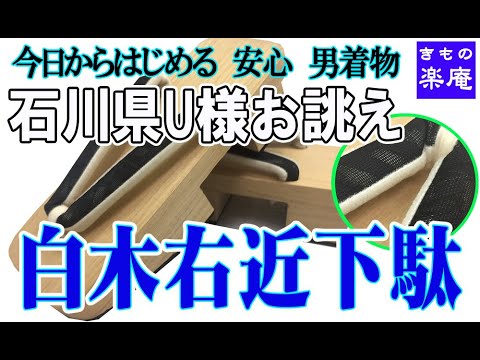きもの楽庵の YouTubeチャンネルでよくお話ししている「着崩れしない着物の着方」をご覧いただいて皆さんにも実践して頂いているのですが、意外とそのコツがご理解いただいていないので、そこのところを重点的に説明させていただきます。
まず、締まり良く苦しくないきもの楽庵オリジナルの無双の伊達締めで骨盤の凹みの位置でキチッと2回、からげるだけだけで止めます。
この無双の伊達締めで締めたら、必ず、襦袢の襟先を持って左右に引っ張り、そして一番重要なコツがこの伊達締めより下の足の方向にお腹辺りに余っている着物の生地を無双の伊達締めの下に引っ張ってお腹の周りをすっきりと襟まわりはピタッと体についている状態にすことがとても大事です。
これで一日着物を着ていて着崩れしなくなります。
たったこれだけですがとても重要なことです。
そして角帯もこの骨盤の凹んだ位置に締めます。
よく着物の本などにある腰骨の位置では高すぎてしまいます。
この位置の体の奥が昔よく言う「丹田」となります。
ここで結んでいると、胡座(あぐら)をかいたり、しゃがむなでと立ったり座ったりを繰り返しても帯が上がってきてしまうなどの気崩れがまったくおきません。
本当に簡単なことですが、伊達締めの下に余分な生地を引っ張っておく事と角帯の結ぶ位置はとても大事なコツです。
文責ーきもの楽庵 代表 児玉哲也